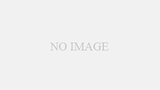はじめまして、バツマルと申します。
経理職で7年ほど働いています。営業、国家公務員を経て現在に至ります。
大学の文系学部を卒業して就職していく人たちの多くは、営業職です。
難関国公立や早慶レベルになると企画経営や士業になる人が結構な割合でいるでしょうが、普通の大学では「まずは営業」というのがスタンダードです。
でも中には「営業は嫌だ」という人もいるでしょう。
営業独特の雰囲気が自分の性格と合わないと、仕事が苦痛になってくることは目に見えていますからね。
そんな、新卒で経理職を目指す人に向けた記事になります。
何となく想像はついているかもしれませんが、新卒から経理になるのはかなり大変です。
うまくいかず、結局営業職にハンドルを切る人の方が多いくらいです。
ですが、まずはできることをすべてやってみないとチャンスは手に入れられません。
この記事で紹介しているポイントをしっかり押さえて、就職活動に挑みましょう!
いきなり経理配属は難しい?
先ほども書きましたが、新卒でいきなりの経理配属は難しいのでしょうか。
答えはYesです。
その理由は次の二つに集約されます。
最初の配属は営業職が多い
普通の会社に総合職として応募して採用されると、ほぼ100%営業に配属となります。
これは求人情報に書いてあることもあれば、書いていないこともあります。
ですが応募する学生側も、「たぶん営業職になるんだろうな」とわかっていることでしょう。
別に営業への就職が簡単とか、使い捨て要因だというつもりは全くありません。
会社の売上は営業がいないと上がりませんし、多くの企業で営業は花形です。
実力のある人はインセンティブがどんどんつきますから、若くして高い年収をもらうことができ、それは経理などの管理部門ではできないことです。
ただ営業は人数が必要なのです。
企業は基本的にモノやサービスを売って儲けないと存続できませんから、それができる営業が多いほど売り上げや利益に繋がっていくわけです。
また営業は実力のある人ほどキャリアアップのために転職していきます。
ストレス、体調不良等の理由で辞めていってしまう人が多いのも事実です。
そうした理由から少し多めに採用せざるを得ない事情もあり、大量採用されているのです。
新卒経理の枠は少ない
対して経理職はいわゆる管理部門で、自ら売り上げや利益を生むわけではありません。
ここに人的コストを掛け過ぎてしまうと、無駄が多くなってしまうのです。
また経理職は専門知識が物を言う部署ですから、新卒で採用するよりも経験者の中途採用をした方が会社としては良いのです。
ノルマがない分、営業に比べてストレスが少なく、転職しようという人があまりいないので採用枠がなかなかできないという事情もあります。
そういった理由から、新卒者を対象に経理部員を採用しようという会社はかなり少ないです。
そこはまず理解しておかなければならない点です。
そのうえで、どういった対策を打っていけば少しでも可能性が高まるのか、ということを考えていきましょう。
事前準備をしっかりしておこう
新卒で経理になりたいのであれば、まずは事前準備をきっちりしておく必要があります。
ここをサボってしまうようですと、もともと低かった可能性が0になってしまいます。
最低限今から書いてあることぐらいはやっておかないと、本気で経理になりたいと思っている人に採用試験で勝てるはずがありません。
どれもそこまで難しいことではありませんので、時間のあるうちから一つづつ潰しておきましょう。
簿記資格は重要
経理になるうえで、やはり簿記の資格はあった方が良いです。
無資格だと仕事ができないとか、採用されないとは言いませんが、確実にライバルの何人かよりは一歩先に行けます。
もちろん3級より2級、2級より1級が望ましいです。1級はかなり難関ですが、2級ぐらいなら時間をしっかりかければ合格できない試験ではありません。
数字に苦手意識がある人は3級から、そうでなければ2級から挑戦しましょう。
2級保持者であれば、ある程度アドバンテージになるでしょう。
合格率は年によりますが、3割前後というところです。
1級を持っていれば経理職として採用したい、と思ってくれる企業はたくさんいます。
そこそこの規模の会社の経理ですら、1級を持っている人はなかなかいません。
もちろん簿記の資格を持っているからといって経理の仕事もできるとは限りません。
資格試験と実践は違います。
ただ、経理に向いているかどうか、経理になりたい本気度を測るための、一つの目安になることは間違いありません。
初学者が2級を勉強するなら3ヶ月、1級なら1年ぐらいは見ておきましょう。
どうしても時間がなく、数字も苦手だ、でも経理がやりたいという人はひとまず3級に合格しましょう。
履歴書には3級保持、2級勉強中と書いておけば、多少のポイントにはなると思います。
伝票入力の練習をしておこう
簿記の資格勉強をしていると、何となく会社のお金の流れについてイメージがつかめると思います。
それでも「伝票を入れる」という作業は、実際にやってみないとピンときません。
一番いいのは、伝票入力のアルバイトで練習しておくことです。
会社の業種によって使う勘定科目は様々ですし、特有のルールがあるでしょうから、伝票入力のアルバイト経験が即役に立つとは限りません。
が、面接で「伝票の入力だけですが、アルバイトとして経験があります」と言えるのは結構な強みです。
経理の仕事は多岐にわたりますが、伝票入力は基本中の基本です。
仕訳を理解し、適切な勘定科目を使って入力する。単純なように思えますが、経理の他の業務を覚えていくうえでのベースになります。
アピールポイントを一つ増やすと思って、アルバイトを探してみましょう。
経理職を募集している企業を探そう
経理の仕事をするにあたって、最も大事なことは「経理職を募集している企業を探すこと」です。
先ほど書いた通り、新卒で経理を募集している会社は極端に少ないです。
できることは限られてきますが、やらないことにはスタートラインにすら立てません。
まずは就職サイトに登録しましょう。
そして実際に経理職の求人情報を検索してみてください。
業種で「経理」に該当するものを選べばOKです。
就職サイトによっては意外とたくさんの求人が出てくるかもしれません。
が、詳しい中身を見てみると、ほとんどが「総合職」としての採用になっていると思います。
つまり「経理としての配属も有りうるけど、どの配属になるかはわからんよ」、
言い換えると「十中八九、営業配属だよ」と読み替えてもらって支障ありません。
ここから「経理職の募集」を抜き出すのは自分で一つずつ見ていくしかありません。
仮に検索結果が500件だったとすると、10件ぐらいしか該当しないのではないでしょうか。
大変根気のいる作業ですし、やっと経理の募集を見つけたとしても、職種以外の条件が自分にマッチしているかどうかも確認する必要があります。
給与や会社規模、立地、福利厚生など、今後長く勤めるのですからこれらの項目はしっかりチェックしなければなりません。
そして良い条件の求人は人気がありますから、多くの学生が応募して倍率も高くなります。
全ての要件を満たすことは難しいと判断したら、少しずつ妥協していくしかありませんね。
この作業をすることで、いかに新卒で経理になることが狭き門かわかると思います。
財務諸表をチェックしておく
面接に備えてのことになるのですが、財務諸表には必ず目を通しておきましょう。
もちろん見ておくだけでは意味がなく、同業他社との違いや特徴、気になった点を面接で話せるようにしておく必要があります。
経理職を採用するための面接では、おそらく「弊社の財務諸表は見られましたか」とか「何か感じたことはありますか」といった質問が来ると思います。
ここで言葉に詰まるようでは単なる準備不足、まず採用されないでしょう。
簡単なことでもいいです。支出の各勘定科目の割合を出してみて、どんな費用が多いのかとか、前年度と全然年度を比べて大きな変化がある点を洗い出してみるとか、そんな程度で大丈夫です。
そこに自分なりの考えをプラスして面接で話せるようにしておくだけで、面接官の印象は違ってきます。
もし財務諸表に関する質問が来なくても、「最後に質問は?」のところで自分から聞いてみましょう。
少ないチャンスをものにするには、積極的にいかないと確実に埋もれてしまいます。
まとめ
新卒から経理に配属されるためのポイントを挙げてきましたが、どれも実践できそうなことばかりではなかったですか?
すべてやったからといって必ず良い結果になるとは断言できませんが、間違いなく前進はしています。
一旦営業として採用されると、そこから経理に異動したり転職したりするのは、新卒で経理になるよりも難しくなります。
もちろん若いうちに簿記1級を取得すれば、未経験でも経理への転身の可能性はあるでしょうけど、それができるのは一握りの人だけです。
経理マンとしてキャリアアップしていきたいのなら、大企業でなくてもまずは経理職になって経験を積むことが何より大事です。
時間のある大学生のうちに、資格取得やアルバイトを頑張っておくことをおすすめします。
今回は以上です!